自分にはできる。志を高く、目標達成!!
誰しも好きな言葉があると思います。それは諺(ことわざ)や格言であったり、造語であったり、誰かから贈られた言葉であったり…。あるいは詩の一節かもしれません…。
私にも好きな言葉はたくさんあります。
今日はその中のひとつ、自分を奮い立たせる言葉、「自己効力感」について書こうと思います。
自己効力感(セルフエフィカシー)との出会い
自己効力感(セルフエフィカシー)という言葉を初めて知ったのは看護学校の心理学の授業の中でした。
心理学の授業ではフロイトやエリクソン、ハヴィガースト、ロジャース等の多くの心理学者や理論について学びましたが、私に最も強い印象を残したのがこの「自己効力感」であり、提唱者のアルバート・バンデューラです。
自己効力感
この「自己効力感」とは、「自分には目標が達成できる」という見込み感(期待感)のことを指すのです。
見込み感(期待感) = 自己効力感
そしてそれは単にプライドが高い、自信があるということではありません。
自己効力感は成功体験によって高まります。「◯◯できたのだから自分には◯◯できる」と経験によって裏付けられたいわば根拠ともいえるでしょう。
自分自身への動機づけ
自己効力感は物事に取り組む際の「動機づけ」によっても高まります。動機づけとは、物事に取り組む際のきっかけです。俗にいうモチベーションを意味します。
これには強い思想や高い目標を持って自発的に物事に取り組もうとする「内発的動機づけ」と、家庭や学校、社会で生活するうえでの規則、義務や、賞罰によって生じる「外発的動機づけ」があります。
では自己効力感が高いとどうなるのか
病院で看護師さんに注射をされる時、「失敗したらどうしよう」と不安そうな看護師さんより、自信にあふれた看護師さんに注射してもらったほうが安心できますよね?
バンデューラによると、この自己効力感が高い人ほど目標達成率が高まるそうです。
これには先ほどの動機づけも関係しています。
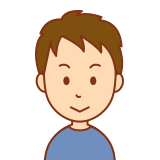
何度も痛い思いはさせたくない。1回で注射を成功させる!
男性看護師A
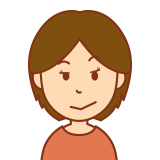
注射苦手でやりたくないのよね。でも私しかいないし…。
女性看護師B
上の例でいうと、男性看護師Aは注射に対して内発的動機づけが行われています。しかし、女性看護師Bは仕方なく注射をするという外発的動機づけが行われています。
仕事や学習、芸術等のあらゆる目標を達成し成果を出すためには、「内発的動機づけ」によるモチベーションを持った人のほうがより成果を出せると言われています。
もし同じ能力の人がいたら?
例えば、身体能力的には全く同じ人間がいたとして、マラソンや野球をしたとします。
すると、自己効力感のより高い人のほうが良い結果を出せる割合が高いということです。自信のある人と自信のない人であれば、スポーツでもゲームでも勝負する前から結果が見えているようなものですね。
自己効力感と自尊感情(セルフエスティーム)
スポーツ選手のインタビューを見ていて、「この人は自己効力感が高いなぁ」と感じることがありますが、そういう人はやはり結果を出しています。
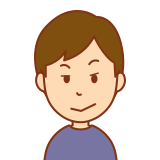
今日の試合、絶対勝てると思っていました。
前に書きましたが、ただプライドが高い、自信があるということではなく、成功体験に裏付けられた自信です‼️
自己効力感の高い人は行動に出ます。スポーツに限らず、仕事でも勉強でもそうです。
何かで失敗しても、困難な状況に立たされても、「自分には目標達成できる」という見込み(期待)が高いので「考え」「努力し」結果を出します。
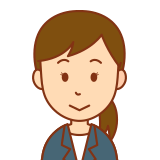
成功体験ということね。
それが見込み(期待)から自信につながり、より自己効力感が高まります。
自己効力感は自己の能力に対する評価であるのに対し、自尊感情は自己の存在価値に対する評価であり、自己肯定的感です。
自己効力感の高まりは自己を価値ある存在であると評価します。
そう、自尊感情(セルフエスティーム)が高まるのです。そして自尊感情が高まることによって、より自己効力感が高まるというプラスの連鎖が起きます。
自分のことを肯定的に認めることができるから、失敗しても、挫折しても立ち直ることができる。また、自分の能力を信じることができる。自己効力感の高い人は自尊感情も高いといえますね。
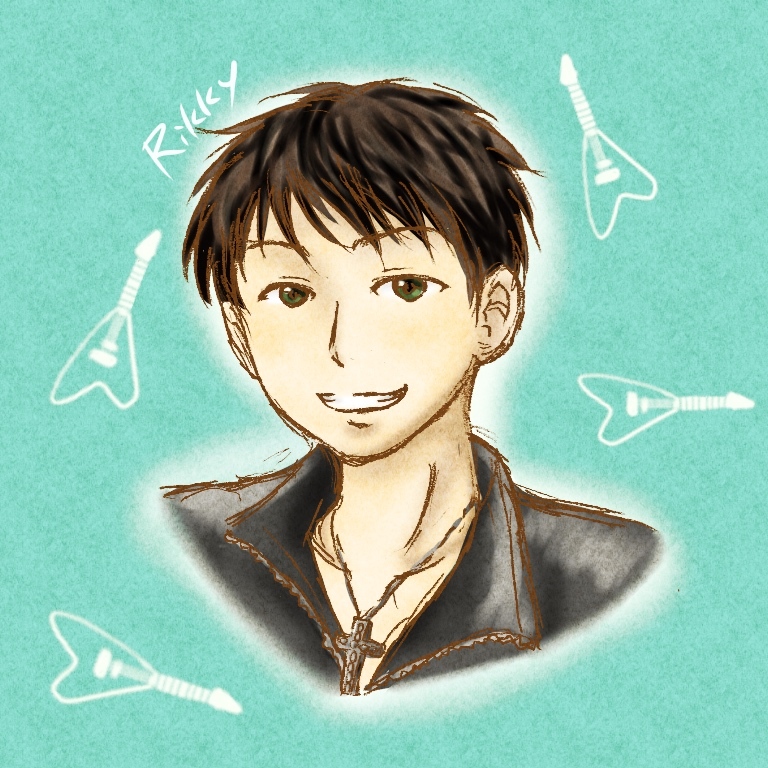
私もギターで名を成したいと思っていた時代がありました。「東京に行くぞ」と意気込んではいたものの、結局行動に出ず…。思えば、ギタープレイに対する自己効力感や自尊感情が低かったのかもしれませんね。
私が体現し実感した自己効力感
これまでうんちくばかり語ってきましたが、冒頭でなぜ「私が好きな言葉」「自分を奮い立たせる言葉」と書いたのか語らせていただきます。
私はバンドマンをやっていたある日、交通事故に遭い5ヶ月を越える入院生活を送りました。そして、恩師との出会いや同じ病室で一緒になった重度の身体障害を抱えた患者さんとの交流によって看護の道を志しました。
そして看護学校に入学し、一生懸命に勉強して初めて受けたテストが解剖学のテストでした。自分なりに努力をし、取った点数は85点でした。小中高校生時代に勉強で劣等生であった私はその点数に大満足でした。
しかし、クラス(40名越え)の平均点は95点です…。そして過去問と呼ばれるこの看護学校の一種の伝統の存在を知ったのです。
過去問とは、先輩が受けたテストを後輩に回しそれを見てテストを受けると全く同じテストなので簡単に高得点が取れるというものです。
私の通った看護学校は働きながら5年かけて正看護師を取得する看護学科があり、病院で働きながら通学する人が多く、病院の先輩にもらったテストを学校でコピーし、クラスメイトに配る人も多くいました。
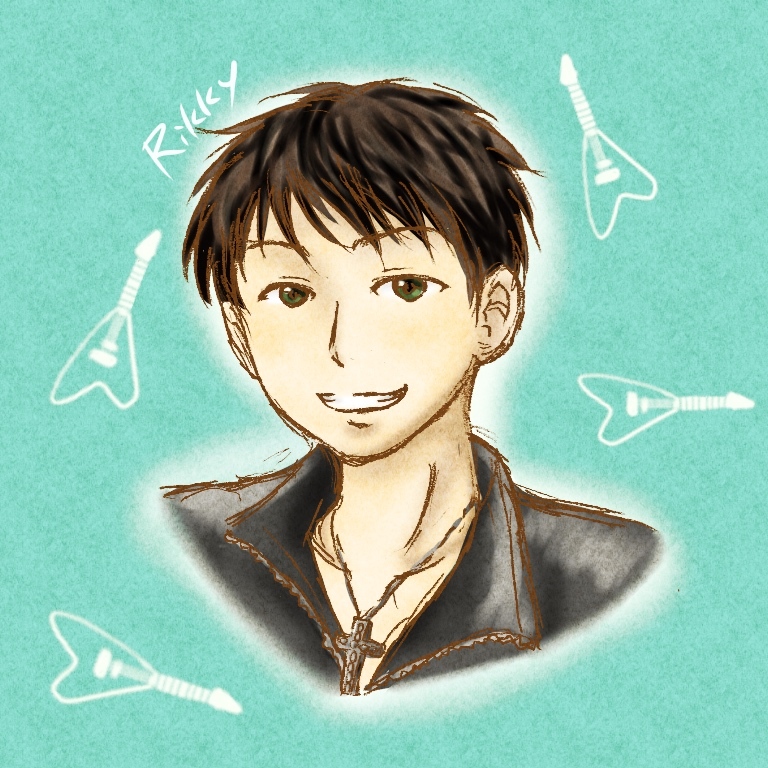
ショックでした…。
看護師になりたいから看護学校に通っているはずなのに、そんなことが伝統になっているなんて…。私は悔しくて仕方ありませんでした。
ある時には図書室のコピー機の中に先輩の受けたテストを取り残したクラスメイトがおり、個人情報保護に対してマスコミで取り上げられていたこともあり、学校で問題になりました。
先輩の「名前」「点数」の記入されたテストがコピーされ、クラスメイトに出回っていたのです。
学校側はそれでも過去問の存在を容認しています。学校の言い分としては「過去問がないと卒業できなくなる生徒がいるから」「最終的に国家試験を合格するには努力が必要だから」と。
私は「絶対に過去問になんか頼らない」「欠点とってもいい、自分の力でテストを受ける」と誓い、5年間の学校生活を送りました。
クラスの平均点が90点以上でも、私のテストの点数が70点台で悔しい思いをしたことが何度もありましたが、その都度「自分のやり方は間違っていない」と言い聞かせました。
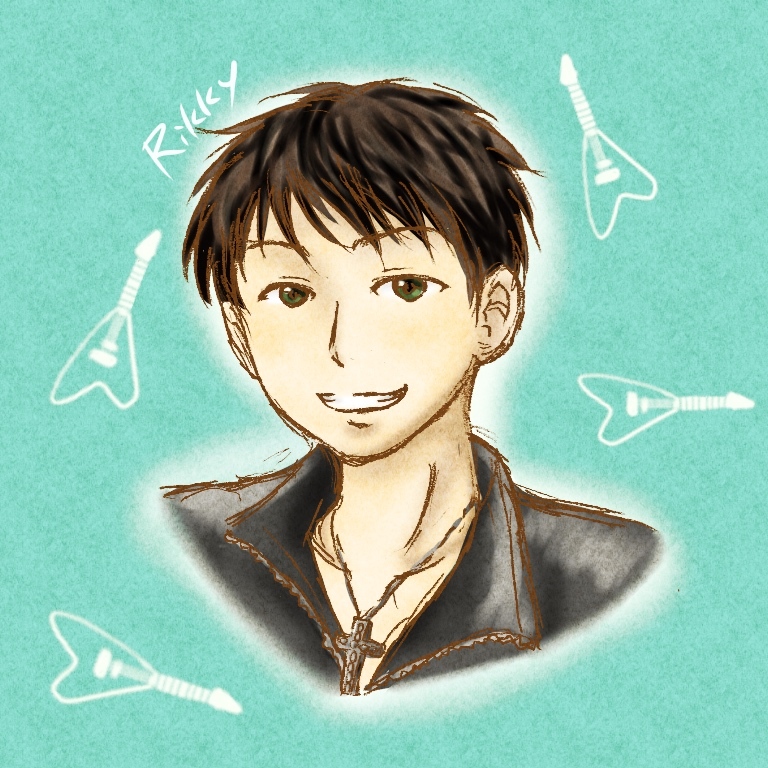
自分で看護師になると決めたんだから、名前も顔も知らない人のテストをコピーしてもらってテストを受けようとは思わない。
小中高と劣等生であった私は、5段階評価の3以上は取ったことがありません。そんな私でも看護学生時代に欠点(60点以下)は一度も取ることなく、平均点90点以上を取った年もありました。
それは、劣等生であった私が初めてのテスト(前述の解剖学)で取った点数によって成功体験を獲得していたことと、看護学校に通う「内発的動機づけ」によって努力したら絶対に欠点は取らないという「自己効力感」があったからです。
過去問に頼る生徒は、過去問ではなく毎年テストを作り直す先生のテストがあるたびに、「私、絶対欠点取りそう」と不安になっている人も多くいました。それは他人のテストに依存し勉強に対する自己効力感を獲得できていなかったからです。
私は5年間、一度も過去問を使わず欠点を取ったことがありません。その努力をクラスメイトも評価してくれていました。しかし、同じ看護師の妻からは「それが当たり前のことよ」と言われました。
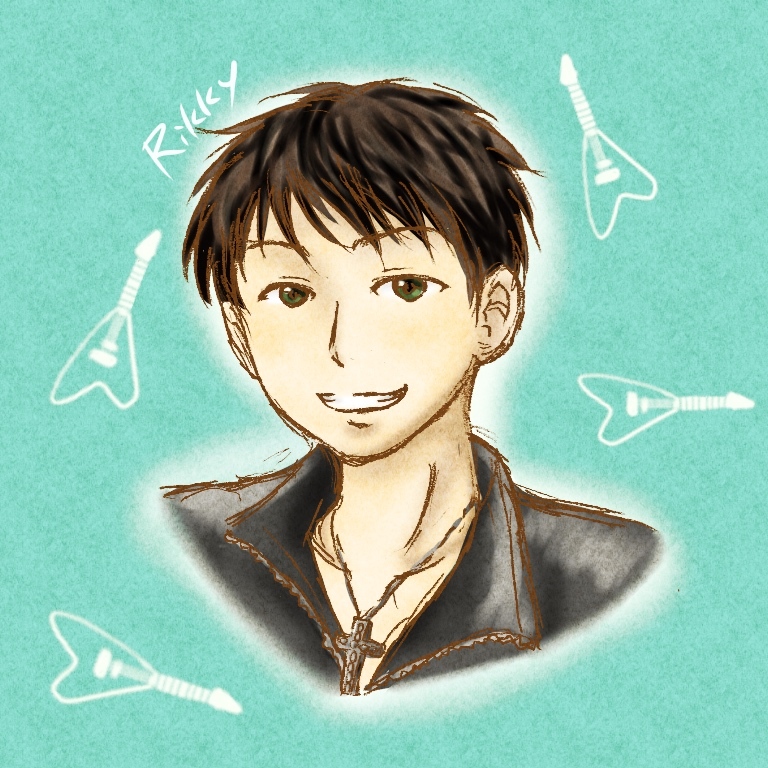
俺は自分の力でテストを受けて、赤点なんか取ったことないよ。(自慢気に)
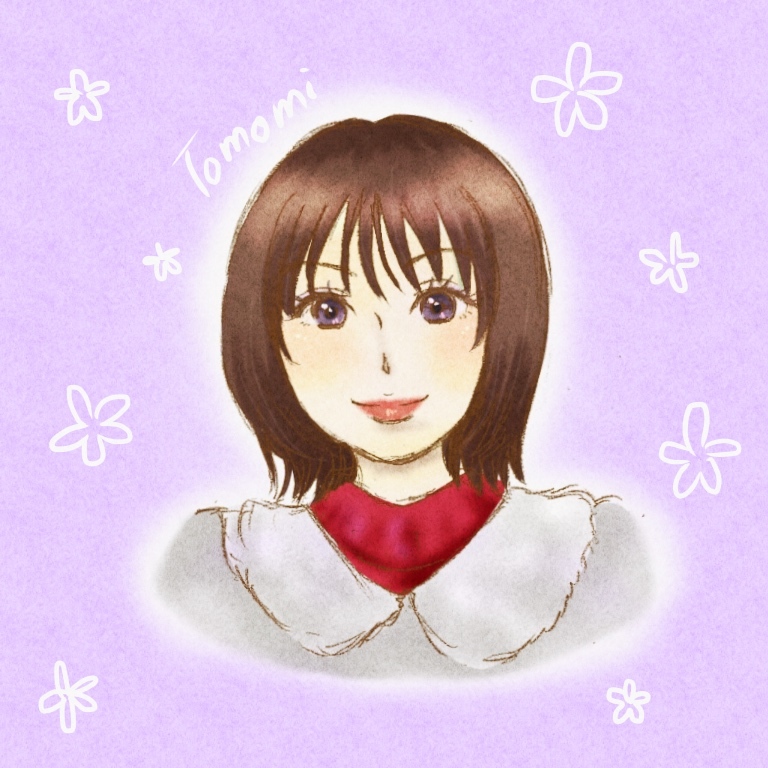
私の学校ではテストが終わるたびに問題が回収されて、過去問が出回ることはなかったは。それが当たり前よ。
過去問を使うのも一つの勉強法という人もいるかもしれませんが、過去の出題傾向を参考にするのと、答えを丸覚えするのは意味が違いますよね。
自分で自己効力感を実践し体現したからこそ言えます。勉強でもスポーツでも芸術でも、仕事でも、自信がない人には「自己効力感」を知ってほしい!
自己効力感は人との相互作用によっても高まる
自己効力感は自分で高めていくこともできますが、他者との相互作用によっても、高めたり、高められたりするのです。
例えば、リハビリによって歩くことが可能になった人がいたとします。
より自己効力感を高めてもらうため、「今日ここまで歩けたから、明日はもっと歩けますよ」といった言葉かけによって、その人の自己効力感は高まるのです。
「明日はあそこまで歩いてみよう」「ここまで歩けたから、もっと歩けるようになるはずだ」と成功体験を他者から承認してもらうことによって意欲的に取り組めるようになるのです。
あなた自身も家族や友人の言葉によって勇気づけられたことはありませんか(^^?
そう考えると、職場や家庭での教育においても自己効力感は大切ですね。
まとめ
こどものやる気や才能を伸ばしてあげるにも、言葉かけひとつで自己効力感を高めてあげられるかもしれません。
職場のハードワークも、部下や同僚への言葉かけによって、思った以上の働きをしてくれ円滑にすすめることができるかもしれません。
私自身、仕事の時はどんなハードワークであっても自己効力感を持って臨んでいます!「絶対に定時で帰ってみせる‼️」と(^^)。
「自己効力感」という言葉が好きって言うと、ナルシストと思われるかもしれませんが、「自分には◯◯できる」って思えることがあるのは嬉しいですよね。




コメント